ソリューション

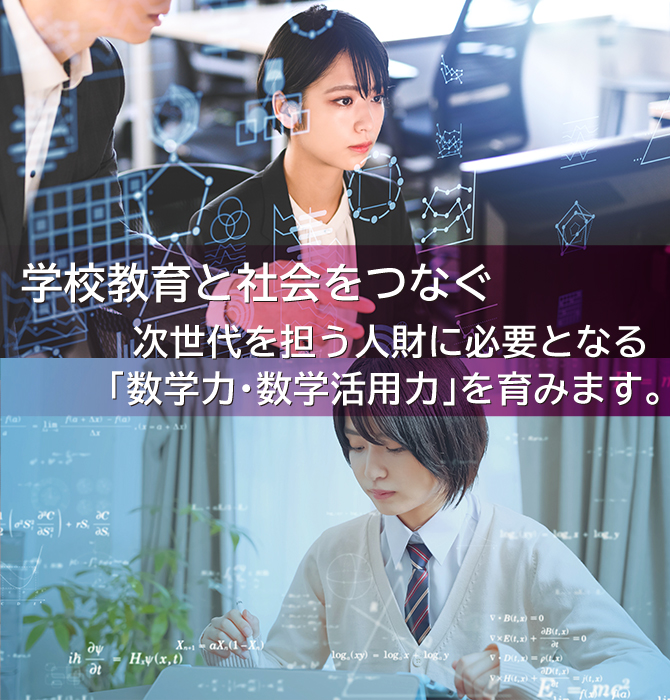
当協会は、「数理・データサイエンス・AI」の基盤となる教科「数学」に関する検定事業や資格制度などの取り組みをとおして、数理・データサイエンス・AIの基礎的素養を兼ね備えたDXを担う人材の育成と活用を推進しています。
支援プログラムについて
当協会のソリューションでは、最初に課題やご要望などについてヒアリングを行います。
それぞれの団体、そこに所属する個々の課題や目的に合わせて、適切なカリキュラム設計を行いご提案いたします。
その一例として、次の支援プログラムをご紹介します。
高等学校・中高一貫校・大学・専門学校などにおすすめの支援
企業・団体などにおすすめの支援
経済産業省「MDASH SUPPORTER」認定
当協会は、内閣府・文部科学省・経済産業省が進める
「数理・データサイエンス・AI教育プログラム」の趣旨に賛同し、
支援する団体として、経済産業省の「MDASH SUPPORTER」に認定されています。
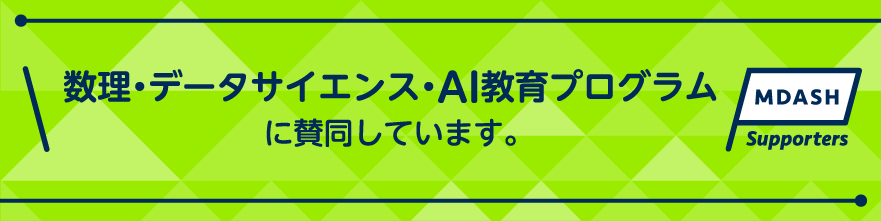
数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度とは、内閣府・文部科学省・経済産業省の3府省が連携し、各大学・高等専門学校における数理・データサイエンス・AI教育の取り組みを奨励するための認定制度です。
政府の「AI戦略2019」においては、データとデジタル技術を活用したビジネスモデルの抜本的な変革(DX)をしていくことが重要で、このDX(デジタルトンラスフォーメーション)を担う人材として、「数理・データサイエンス・AI」を理解し、活用できる人材が必要であるとしています。これらを身につけた人材を育成するしくみとして、大学(大学院を除く)、短期大学、高等専門学校が実施する教育プログラムを認定する「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度」が創設されました。
経済産業省から認定を受けた「MDASH SUPPORTER」は、数理・データサイエンス・AIに関する基礎的な能力を修得した人材がより多く輩出されることを期待する産業界の声を集めることを通じて、大学・高等専門学校での教育プログラムを整備する取り組みを後押しするとともに、人材の活躍の場が拡がることを目的としています。
特集
国や経済団体による「数学」教育改革や、人材育成に関する見解の一部をまとめましたのでご覧ください。
導入事例
当協会のソリューションの導入事例をご覧になれます。
代表メッセージ
お問い合わせ・資料ダウンロード・導入の流れ
各企業・団体にあわせてカスタマイズした支援プログラムを、ソリューションとしてご提供いたします。下記のフォームから、ご相談・お問い合わせください。
また、資料ダウンロードご請求フォームから、「ビジネス数学」「データサイエンス数学」に関する各種資料がダウンロードできます。
ソリューションについての
お問い合わせフォーム
資料ダウンロード
ご請求フォーム
導入の流れ
-
お問い合わせ
お問い合わせフォームに必要事項をご入力ください。
当協会の担当者から、7営業日以内にメールまたは電話でご連絡いたします。
-
ヒアリング
現状の課題やご要望をヒアリングし、適切な支援プログラムの選定のお手伝いをいたします。
オンライン・対面のどちらの形式でもお打ち合わせが可能です。
-
ご提案・お見積り
ヒアリングの内容をふまえ、プログラムなどをご提案いたします。
概算のお見積りなども、あわせてご提示いたします。
-
お申し込み
内容・日時などの詳細が決まりましたら、支援プログラムの発注申込書のご提出をお願いします。
カスタマイズも承ります。
-
導入・実施の準備
プログラムの内容により、テキストなどの準備をいたします。
そのほか、導入・実施に向けて必要に応じてお打ち合わせを行います。
-
導入・実施
支援プログラムを実施します。
-
導入・実施後の
フォロー・ご請求導入・実施内容を振り返り、今後に向けたご提案をいたします。




